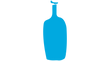変化を恐れず、他者にオープンであること 創業者ジェームスから受け継いだブランドの真髄
Blue Bottle Coffee Japan 合同会社代表 伊藤 諒 退任インタビュー
Blue Bottle Coffee Japan 合同会社代表として9年間チームをリードしてきた伊藤 諒が、2024年8月末で退任することを決め、そのバトンがエリック・ジェンキンスに渡される。創業者ジェームス・フリーマンから受け継がれる哲学が、また新たなフェーズとして未来へと繋がる。このバトンの引き継ぎのタイミングでオープンした豊洲パークカフェにて、お二人の思いをインタビューしました。
一人称で自分の好きを語ること
―まずは、退任が近い諒さんの今の心境を聞かせてください。
伊藤:今日は豊洲パークカフェのプレオープン日なんですが、出店準備のモードに入るといつもと変わらないです。これまでと同じように、オペレーションの気になる部分を指摘したり、あまり自分がいなくなることは意識しないまま、日々が過ぎている感じですね。ただ、やはりふとしたときに、溢れるものはあるというか。豊洲のメンバーにも創業時からの仲間がいて、このメンバーでこれまで何店舗開けたんだっけ、あっこれが自分のラストか、と思う瞬間はあります。でも基本的にはいつもと変わらず、大丈夫だなという感覚です。
あとこの数ヶ月間、次にバトンを渡すエリックと過ごす時間が長くあったのも大きいです。僕らにとって新店オープンはコア中のコア。ディテールを大切にしてお客様にどういう体験を届けるかという意味において、空間、プロダクト、コーヒーの味のすべてをデザインして、ホスピタリティからくるおいしい時間を生み出す。
そこにブランドのすべてが凝縮されているので、その作り込みのプロセスをエリックと一緒にできている安心感はすごく強いですね。同じ時間や体験を共有することは、これまでもチームで大事にしてきたことで、例えばいろんなものをブランドチームと一緒に見に行って、あのときのあの感じって言葉にはできないけど共有している体験があって分かり合える部分が、ブルーボトルコーヒーのブランドを繋ぎ止めていると思っていて、エリックともそんな時間を持てているのはすごく幸運なことだなと思います。

ブルーボトルコーヒー 豊洲パークカフェ
photo Takumi Ota
―諒さんがブルーボトルコーヒーにジョインしたきっかけを教えてください。
伊藤:きっかけは僕が商社に入ってアメリカの大学院にMBA留学していたときに、友達がブルーボトルコーヒーで働いていて、創業者のジェームス・フリーマンの日本の喫茶店文化への思いもあって、ちょうど日本オープンが決まったタイミングだったんです。ただ内部に海外展開や輸出入をやったことのある人がほとんどいなくて、その友人から「ロゴ入り紙カップが日本の税関で止まっちゃって動かないんだけど、諒は商社だから、どうしたらいいかわかる?」って相談の電話がきて。
話を聞くとそもそも書類が揃ってないから揃えて、税関に直接行って拝み倒したら間に合うから、もう2週間でオープンなら早く行ったほうがいいとアドバイスしました。その後、清澄白河ロースタリー&カフェオープンの2日前に紙カップが間に合って、なんとなくそこで「この人、日本のビジネスわかってそう」という幻想が生まれて(笑)、インターンにさそわれたのがきっかけでした。最初は物流のサポートから始まり、カフェ運営に関わる全般を当時のジャパン代表の井川沙紀さんと直接やりとりしながら進めた3ヶ月が大きかったですね。
少し生い立ちの話をすると、子どもの頃から父の仕事の影響で、何カ国かを渡り歩いて育ってきて、いろんな国の人と友達になって家族みたいになってという経験があるなかで、一方世の中は紛争や戦争が絶えない。それって間にある誤解や先入観からきていて、ずっとチームスポーツをやっていたので、チームを作って同じ目標に向かって絆を作ればそういった先入観がなくなる。じゃあそれを一番自由に作れるのはビジネスの世界だから、ビジネスの世界に入っていろんな人とチームを作りまくれば世の中もっと平和になるなと、学生時代に思ったんです。それで、どんなビジネスかわからないので、なんでもやっている総合商社に行こうと。
そういう意味では、ブルーボトルコーヒーに出会ったときに、コーヒーが大好きなジェームスがいて、カフェのデザインにこだわる人も、ビジネスとしてスケールすることにパッションを持っている人もいる。それが100/0じゃなくて、みんなのいいところを集めて特別なものを作ろうよって考えているカルチャーや人に惚れ込んで、そこでもう心が動いちゃってフルタイムジョインしたのが2016年のことです。

―特に思い出に残っていることは何ですか。
伊藤:創業者ジェームスとの思い出は結構ありますね。自分にとってセンセーショナルだったのが、入って間もない頃、春にジェームスが日本に来ていて、待ち合わせしてミーティングしようって約束してたんです。そこにジェームスから「ごめん、今日の打ち合わせはキャンセルさせてくれ」って電話があって「どうしたの?大丈夫?」と聞くと、「いま目の前にある桜が美しすぎて、僕はここを動けない」って言われたんです。最初は「何言ってるんだろう、この人は」って感覚で(笑)、僕のすごく左脳的なロジカルな世界ではない発想だった。だけど、僕とのミーティングを決して軽んじてるわけじゃないのは伝わっていて、その瞬間のこの光、この風、この桜の咲き具合って、この一瞬しかないから、これを逃したくないという彼の“人生で何を大事にするのか”みたいなことにすごくハッとさせられました。その瞬間にしかないものに集中することの大切さを、その後ブルーボトルコーヒーで働くなかで多く感じるようになったのは、あれが転機だったなと思います。
あと自分個人としては、すごく人の目、まわりの目を気にしていた時期があって、それまで大学に入って体育会で部活をやって、大企業に入ってMBA留学してと「こうあるべき」という期待値を背負っているところがありました。ブルーボトルコーヒーに入ってからも、ジェームスと沙紀さんというクリエイティブがっつりでブランドを形作っている人がいるから、自分は常に冷静でパッションとかではなく、課題をロジカルに解決してすべてを着地させていくことが役割だと考えて、何かを好きかどうかを表現することの苦手意識もあって、気持ちを出してなかったんですよ。
だけど、ジェームスや建築家の長坂常さんと仕事しているなかで、ブルーボトルコーヒーに関わる者として、一人称でデザインや感性というものに対して語れることがすごく大事だなと思うようになって。自分がどういうコーヒーが好きか、どういう空間をいいと思うかを、合っている間違っているではなく表現すること。以前はそれがまわりに「いいね」と言ってもらえることを目指して、正解を求めている感じだったんですが、それがブルーボトルコーヒーとして採用されるかどうかは別にして、自分の意見として、これが好きというのを素直に言えるようになっていったのは、ジェームスと仕事してきた影響が大きくて、彼がすごく勇気づけて引き出してくれたところです。
韓国に一店舗目をオープンさせたとき、いろいろトラブルがあって、店内の商品まわりの照明の当て込みを素人ながら自分の感覚で全部やったことがありました。それにジェームスが最初に気づいてくれて、すごくいいと褒めながら沙紀さんに「諒も、僕らの言語がわかるようになったね」と。コーヒーに対しても意識が変わって、自分なりの意見をようやく言えるようになってきたときだったので、自分の好きをちゃんと大事にする根本が身に沁みて、韓国の街中で涙が止まらなかった。ブルーボトルコーヒーにはゲストに対しての接客マニュアルがなく、コミュニケーションをしながらゲスト自身の“好き”を探すお手伝いをしている感覚が強いんです。
コーヒーをどれにするかって、人生にとっての重大なライフチョイスじゃないけど、そういう細やかなところから自分はこれが好きっていうのを選択する。そうすることが人生にとってすごく素敵なことなんだということを、こだわりや好きが詰まったカフェから社内外に発信してきたブランドだと思うので、僕自身もブルーボトルコーヒーで働くなかで教わったことは大きかったです。

ブルーボトルコーヒー 京都カフェ
photo Takumi Ota
自分を変化させることを恐れない
―特に思い入れが強いカフェはありますか?
伊藤:京都はビッグプロジェクトだったり、三軒茶屋は僕が場所を探して、デザインプロセスも全部やってオープンした初めてのお店ですごく思い入れがあったりするんですが、それぞれにストーリーがある特別なものなので選べないですね。
でも今日の豊洲パークカフェもそうですが、ひとつのカフェを全員で作っていくために、そこでオープンするに至ったストーリーをブランドチーム、デザインチームからカフェチームのバリスタ1人1人に至るまで、ひとつのファミリーとしてシェアするようにしたのは、すごく意味深いと思っています。その共有オリエンテーションを行う進め方を始めたのが4年前の京都カフェオープンのときからですね。
ブルーボトルコーヒーに入って、自分自身の個人的なテーマとして「いろんな人を繋ぐ」というのが常にあって。本社とカフェの距離をなくしたいし、繋がりが多ければ多いほど、特別なものができるチャンスが広がると思っていて、各チームを繋ぐことはすごく意識してきました。定期的に店長や副店長になるメンバーは製造部門に研修に行くという制度を作ったのも、そのひとつ。賞味期限のあるものを扱っているので、発注ロスは出ます。そのロス率を何%に抑えろ、発注精度を上げろというのはすごく簡単なんだけど、それによって顧客体験に影響が出ちゃうと意味ないなと思っていて。それが発注する責任者が製造する場所で1日でも働けば、こんなに手数が込んでいるものを自分たちの仲間が作ってくれているんだとわかるし、だったらちょっと気合入れて無駄がないようにしようと思いが繋がる。そのほうが発注精度をゴールとしてKPIを設けて、あなたの評価はそれによって行われますと言われるより100倍長続きするし、本質的だと思うんです。
うちの仲間の◯◯が作ったクッキーなんです、という接客だったり、僕はそれぞれのカフェの場面すべてに立ち会うことはできないけれど、自然と無駄を出したくないって思いになるから。次もしよかったらどうですか?と試供するサンプリングも、残り何時間になったら出していいよって許可制にすると自発的に考えなくなるけど、そこはできるかぎりカフェの現場に近いメンバーが自分たちで考えてアクションできる余裕を持てるようにして、本質的に何でやっているかという思いを“繋ぐ”というのは意識しています。
―諒さんは「なんのためにやるのか」「WHYを伝えられるようにしてほしい」と常に発信されていたように思います。諒さんに代表のバトンが渡ってから、特にチームプレーでの仕事が楽しくなっていった印象があります。

ブルーボトルコーヒー 京都カフェ
photo Takumi Ota
伊藤:チーム感は意識していましたね。経営者ということでいうと、甘いといわれる部分も多分にあると思うんです。人を信じて裏切られることもありますよね。それってダウンサイドとしてリスクだから、そう考えるとすごく小さいチームに絞って、裏切られるリスクをコントロールするって考え方もある。
だけど、信じて迎え入れて一緒にやろうとしたときに、予想しないくらいのサプライズが生まれることのほうが、これまでの人生経験上多かったので、そこを信じたいという気持ちは強くあります。その意味では情報の開示もすごく意識的にしていて、出店情報などブルーボトルコーヒー社員はリリース前に全員が知っている。それって情報が漏れるリスクを考えるとやらないけれど、「ファミリーだから、みんなには知っていてほしい。なぜこの場所につくるのか。エキサイティングな話だから、みんなに知っていてほしいけれど、もし漏れたら本当にダメージが大きいから頼むよ」って気持ちで。それでこれまで情報が漏れたことはないし、そのほうがみんなが自分ごとにできると思うんです。自分で考えて、自分でアクションを取れるのがブランドにとって一番大事だし、その意味では自分ひとりでコントロールすると自分以上のものにはならないので。
ブランド構築だったらブランドチームのメンバーもいるし、コーヒーを作ってゲストをもてなすのだったらカフェチームのほうができるし、だとしたら、そこを頼って大きくしていくときに、ひとりの人間が判断する範囲を分散したほうがいいなというのは、あるときを境に切り替えていったところです。そっちのほうが楽しいですよね。
僕がジェームスと働いて感じたところでいうと、端からみるとすごく強いこだわりを持った創業者で、彼の言うことがすべてという時期も過去にあったとは思うのですが、彼自身はもっと自分だけだと辿り着けないサプライズを見たいという気持ちが強いんじゃないかと思います。それは僕らも同じで、例えば対外的なパートナーとして長坂常さんに「このカフェのテーマはこれだからカラーパレットはこれで、この素材を使ってほしいので、この中でやってください」というお願いの仕方はしない。すごくふわっとしたかたちで才能のかけ合わせができる状態を大事にしていて、そのためにはぶつけられるだけの自分の意見を持ってなきゃいけないんだけど、それをジェームスにぶつけると彼は「そういう考えもあるんだね、じゃあこういうことかな」という受け入れをすごくやってくれていて。
だからブルーボトルコーヒーというブランドの真髄って、自分を変化させることを恐れないことと、まわりの意見に対して、それが本気の意見であればなおさらオープンであることがコアになっていると思います。そこの強さをジェームス・フリーマンという人間はすごく持っているから。自分が築き上げてきたものを変えるってすごく怖いことのはずなのに、何か新しい方法が見つかったら、今日からはこっちのほうが絶対いいじゃんみたいに、変えることにまったく抵抗がないんですよ。それが彼のめちゃくちゃ人間的な魅力だし、強いなと思う部分。そういうマインドは、あらゆるところにチームとして持ちたいと思ってきました。
―ジェームスは日本上陸当時には、今よりもっと日本に来ていて直接コミュニケーションする機会がたくさんありました。その生の声を聞いている人たちが諒さんをはじめとして、いまだに何人も現場に残っていて、このプロジェクトでこういうことをやるとジェームスは喜んでくれるかなって、いつもどこかで思って仕事をしている。今回の豊洲パークカフェのオープンムービーのSNSにも、一番はじめにジェームスがコメントしていて、“Beautiful”とひとことあって、それを見た瞬間、本当に嬉しく感じる文化がチームにありますよね。
伊藤:あと思い出深いところでいうと、僕が代表になってすぐにコロナ禍に入り、業績が厳しくなった時期がありました。それでも特に最初は数字のガチガチの話って、あまりカフェメンバーにはしなかったんですね。というのも、それを意識しながらゲストと接すると、絶対にホスピタリティに影響が出ると思ったから。たとえばゲストとの対話のなかで感じた気持ちで商品をおすすめするのと、ここで客単価を取っておかないとやばいなって意識があっておすすめするのとでは、100%本質的なところからブレてしまうので。とはいえビジネスと両輪なので、ビジネスを回していくということも徐々にみんなに意識してもらわないといけないし、一生ブルーボトルコーヒーで働くだけが人生じゃないから、外に出たときにも通用するような人になってほしいというのもあって悩んでいました。
そんなコロナ禍でも、だんだん1時間に1回は換気するとかして、月に一度は店長が集まれるようになったんです。その場で、結構数字が厳しくて、今年あとこれくらいプラスにしないといけないという状況で、数字について控えて話していたときに、一番古株の店長がパッと立ち上がって「諒さん、いい加減、僕らのことを信用してください。いくらトップラインを伸ばさないといけないのか言ってほしい」といわれたんです。それで正直に伝えたら「まじっすか、聞かなければよかった(笑)」って。そのときに、チームとしてすごく骨太になってきた感覚がありました。
ブルーボトルコーヒーってすごくピュアなことをやっているブランドではあると思うんです。おいしいにこだわるとか、なんとなく好きでここに来たいとか、心を動かすことをやっているけれど、それだけじゃなくお金の話もちゃんとわかって武器にしようよって部分をどこかのタイミングで両立できるようにしていきたいと思っていたこともあって、それが店長クラスでできるようになってきたと思えた瞬間で、すごく嬉しかったですね。
―それはぐっとくる話ですね。これから諒さんからエリックさんにバトンが渡されるタイミングになりますが、どういう思いで託されるのか教えてください。
伊藤:「ない」と言ったら変なんですけど、僕がエリックの立場だったらいろいろ言われたくないだろうなって思いもあって、その意味では、大前提としてこれまでエリックと時間を過ごしてきたなかで、表現の仕方は違っても、ビジネス経験は僕よりもあるし、いろんなブランドを渡り歩いてきた面でも僕より引き出しも多いなかで、これから新しい展開をどんどん見せてくれる人だと思っています。またさっきの話のような、変化することに対して痛みを伴うから嫌だという気持ちもまだありながらも、それを楽しもうと思えるチームにブルーボトルコーヒーとしてなりつつある。その意味では、僕が考えていることも日々チームには十分に伝えてこれたと思っているし、エリックともこの2ヶ月、一緒にアメリカに行ったり、話すなかですごく意識が擦り合ってきている感覚もあって。よく誰かがチームを去るときに「もうみんななら大丈夫だよ」って言うシーンが一般的にあると思うんですが、それは僕は絶対に言いたくない。すごく無責任な感じがするから絶対に言わないんだけど、僕がいなくなることでのインパクトが少なからずあったとしても、そこを穴埋めするためにエリックが来るわけではないし、僕がいなくてもみんながこれまでやってきていることの実績はそれよりも遥かに大きいと思う。そこに新しいリーダーとしてエリックが加わることで、全然違うブルーボトルコーヒーになっていくべきだと思うし、それはこれからの1日1日の積み重ねで、振り返ったらあのときと変わったねということだと思います。
あともうひとつ絶対に言いたくないと思っているのが、辞めるときに「これからはいちファンとして」っていう台詞。あれすごく嫌いなんです(笑)。僕のなかで去る者が言うことじゃないなって自分でもツッコミを入れながらですが、一回本気で向き合ってファミリーになったら、もう一生ファミリーだと思っているから、ファンという距離感じゃない。そういう意味では、いま一緒に仕事をしているメンバーに何かあったら、いつでも僕でよければ連絡してほしいし、僕はもう一生自分はブルーボトルファミリーだと思っているから、これからもカフェにも行くし、バトンを渡したから終わりって感覚はないんです。エリックには、ジョインしてくれてありがとう、みんなをよろしくっていう感じが正直なところだと思います。

ブルーボトルコーヒーの心がすべてのカフェにある
―諒さんからのバトンを受け取って、エリックさんの思いを聞かせてください。
エリック:この2ヶ月、諒さんと一緒に時間を過ごしながら、ブルーボトルコーヒーの心を教えてもらってきました。今日の話を聞きながら、振り返ってみるというコンセプトでシェアさせてもらえたらと思うことがあります。私自身、10年くらい前から、ずっと常連客としてブルーボトルコーヒーに通っていました。
青山カフェのオープニングを偶然見かけたのが最初で、そのときから週3、4回は訪れていて、ずっと前から家族みたいな思いです。ですから、その意味でもこの素晴らしいブランドを育ててきた諒さんとそのチームに出会えて嬉しいし、引き継ぎ期間として裏側からみて、なるほど、だからこういうブランドができているんだと感じられて、すごく感謝しています。この10年間でもいろいろな成長があったことを知りましたが、子どもが育っていくのと同じように毎日見ているとあまり気付けないケースもある。でも子どもはあっという間に大人になるんですね。それと同じように、常連として毎日ブルーボトルコーヒーを見ていましたが、そのチェンジに気づいていなかった奥深い部分も知っていくことで、これから本当にその家族の一部になるんだという感情でいっぱいです。
英語の直訳になりますが、いい意味での“Heavy Responsibility”を感じています。なぜかというと、自分が何かしたいからチェンジするというわけではなく、ブルーボトルコーヒーの心もあり、ゲストの心もあるから。そしてジェームスの美しい花の前に立っているから別の日に話そうというエピソードに戻りますが、それと同じように、その瞬間の素敵なことをちゃんとわかってくれている会社だと思います。ジェームスの例をシェアしてくれたんですが、諒さん自身もそうだと思いますよ。6月に一緒にアメリカに行かせてもらった一週間はすごく印象的でした。それまで私のブルーボトルコーヒーの経験は100%日本でした。なので、アメリカのカフェを巡りながら、諒さんからジェームスの話やブルーボトルコーヒーの歴史を教えていただきました。それは本当に素晴らしい経験でした。このデータがどうとか、情報を伝えるという感じではなくて、実際に街を散歩しながらジェームスゆかりのスーパーマーケットでアイスを買って、近くの公園で食べながらその場所にまつわるエピソードを教えてもらったり。そのときから本当に、私が思った以上にブルーボトルコーヒーが心のある会社だと理解できるようになりました。また、諒さんがどれほどこの会社とチームメンバーを愛しているかも理解できるようになりました。チームメンバーの心の細かなディテールまで話す諒さんの言葉を聞きながら、本当に私がこれくらいできるのかと心配したほどです。2ヶ月間と短い期間ですが、十分に思いが伝わって感動しています。そしてこれから、私もファミリーの一部として、毎日ブルーボトルコーヒーのブランドのことを考えながら、ゲストのことを考え、どういう風にブルーボトルコーヒーの世界観を伝えられるかをみんなと一緒に考えていきたいなと思っています。もちろん歴史を守りながら、みんなの努力を守りながら、カフェのなかだけじゃなく外からもブルーボトルコーヒーの印象をどうやって広げることができるのか。着任してから一週間も経っていないなかですが、本当に私が諒さんとブルーボトルコーヒーの全員からのスピリットを感じているので、それを通じて私の力だけじゃなく、チームの力でみんなと一緒にもっと強くしていきたいと思っています。

ブルーボトルコーヒー 青山カフェ
―エリックさんにとって青山カフェは週に3、4回通うようなお気に入りの場所だったわけですが、どこが他のカフェと違っていたのでしょうか。
エリック:みんなと同じくコーヒーが大好きで、ずっと前からたくさんのカフェでコーヒーを飲んできましたが、青山カフェは「ここは何なの!?」とまず雰囲気やデザインに魅了されて、毎回例外なく素敵な経験ができました。みんなすごく優しくて、コーヒーもおいしくて、空間も素晴らしい。全部にチェックがつくような体験で、そんな体験をさせられるブルーボトルコーヒーという会社だったら、私はジョインしたいと思うようになったんです。
これほど愛せるようになるブランドって、それを作っている人の心がそのブランドに入っているなと思っていて、私もそれを一緒にできたらなと思っています。でもそれは青山だけじゃないよ(笑)。今日は六本木の気分かな、渋谷、広尾かな、とカフェを巡って、それぞれ異なるカフェデザインや限定メニューを食べて楽しんでいるのですが、どこのカフェに行ってもブルーボトルコーヒーのスピリット、心は同じでした。先週、初めて関西のブルーボトルコーヒー カフェに入ったのですが、神戸でも京都でもどこに行っても「ただいま」みたいな感覚で、心がすべてのカフェにあるなと思ったんですよ。

ブルーボトルコーヒー 青山カフェ
―デリシャスネス、ホスピタリティ、デザインという、ブルーボトルコーヒーが考える豊かなコーヒー体験の3要素を、エリックさんは実際に以前から感じられていたんですね。
エリック:これは本音で、ブルーボトルコーヒーからのオファーの連絡は、運命のようでした。ずっと家族みたいに感じていたところに入れるチャンスがあるのだと、人生においての素晴らしい経験になりそうだからやってみようと。そんな非常に嬉しい思いですが、諒さんの最後の2ヶ月を一緒にすごして複雑な気持ちもあります。半分は諒さんが卒業することで私が入れることになった喜びですが、半分は卒業することで彼と一緒に仕事をできなくなる寂しさ。ファミリーの一部になったので、本当にみんなと話しながら、諒さんが大切に育ててきたブランドを、どうやって一緒にこれからも育んでいくか検討していきたいと思います。
―ブルーボトルコーヒーに入ってみて、まだ日は浅いですが、新たな気づきはありますか?
エリック:中から見て、想像以上で嬉しい気持ちです。私がゲストとして毎回カフェに入ったとき、愛が感じられたというとおかしく聞こえるかもしれないけど、本当にそれを感じられたんです。ブルーボトルコーヒーは、そのような気持ちを与えられる会社です。
こんなカフェをつくる人は、やっぱり心ある人だと思います。入って1週間だから、全員にはまだ会えていないのですが、チームメンバーに会うたびに「よろしくお願いします!」という挨拶からスタートして、やっぱりこの人もその気持ちを生み出す一部なんだと理解していって、話せば話すほど「ああなるほど、だからこういう答えに行き着いたのか」「こういう発想があったから、これを継続しているんだ」と毎回発見があって、ちょっと子どもっぽく聞こえるかもしれませんが、本当にワクワクしているんです。
伊藤:僕も9年間ワクワクしっぱなしなので、その思いは共有できると思います(笑)。ブルーボトルコーヒーの代表として、ラジオなどで話す機会はありましたが、今日のような話はあまりしたことがなかったので、改めて自分の思いを確認することができました。退任することで、社内のみんなへの感謝も含めて思いを伝えられたらということと、エリックにバトンを渡すうえで、立ち帰れる場所を残せればと思ってのインタビューでしたが、ちゃんと言葉に出すというプロセスのなかで、僕自身が救われたというか、すごく意味のある時間をありがとうございました。途中ちょっと感情が高まって、込み上げてくるものがありましたが(笑)。
―組織の人間関係としてすごくフラットなブルーボトルコーヒーの環境は、諒さんが相当意識して作ってくれたものなんだと改めて実感する機会でした。安心感があるからこそ一人称の意見を言いやすくてコミュニケーションが成り立つチーム文化。諒さんの前には井川沙紀さんがいて、創業者のジェームスと一緒にみんなで作り上げてきたものにゲストとして感動したエリックさんがいて、ファミリーとしてジョインして、未来へと繋げていく。これからも受け継がれてきたものを大切にしながら、進化していく過程をみせていければと思います。
伊藤:そういえば、エリックとアメリカに行ったとき、僕よりブルーボトルコーヒー歴が長いジョンというCFOと一緒に話していて、同時に僕とジョンが言った言葉があって。エリックが「ブルーボトルコーヒーにそれだけ長い間いて、どういうところが好きですか?」って質問をしたときに、2人同時に「いやなやつがいない!」って(笑)。そこは本当に、今日の豊洲パークカフェのプレオープンを見ていても思うんですが、いいやつばっかりなんですよ。愛情深い人がすごく多い。ちょっとでもカフェに興味を持ってくれている人を見かけたら、誰かしらパッと店外に出てご案内するとか、困ってそうな人がいたらヘルプするとか。本当に愛情深いメンバーが揃っていて、そこに帰結する。もちろんデザインが素晴らしいことも大事だし、コーヒーがおいしいことも大事だし、スキルが揃っているのも大事だし、全部大事なんだけど、根本に愛情がないとそれってまったく生きないし、継続はできないから、愛情深い人がブルーボトルコーヒーには多いというのは、僕がすごくいいなと思うところです。
Text: 大澤佑介 RCKT/Rocket Company*