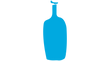常に変幻自在な自分でいるために、自然が教えてくれること
写真家 石川直樹
Blue Bottle Coffee Japan 合同会社代表 伊藤 諒
「旅をするってことは、身体を通じて世界を知っていくっていうことだと思う」。そう話すのは、写真家として、北極圏からヒマラヤまで、あらゆる場所を旅しながら作品を発表し続けている石川直樹さん。ブルーボトルコーヒーのジャーナル『SmallTalk』の発刊記念として、代官山カフェにて伊藤諒とのトークイベントをおこないました。自然のなかに身を置くことで自分自身と世界を改めて見つめ直す体験をした2人が、旅と写真とコーヒーについて語ります。

新たな自分に出会える場所
石川:伊藤さんは、最近頻繁に山や川に行かれるようになったとおっしゃっていましたが、アウトドアでの活動を始めたきっかけはどんなものでしたか?
伊藤:3年前くらいに友人に誘われて、西穂高沢に登って、自然の音しかない空間に身を置いたときに言葉では言い表せないぐらい気持ちが浄化されたんですよね。もっとこの世界を見てみたいっていう衝動にかられました。登山の過程で、全然知らない人なのに挨拶したりするのも、普段都会で生活している自分にとっては新鮮な感覚で、山ならではの文化とか場の力みたいなものにも惹かれました。
石川:確かに、山と人の関わりというのは、面白いテーマですよね。登山の成り立ちも日本と西洋では異なっていて、西洋では山の頂上に立つと、その山を“征服する”、“制覇する”などという言葉を使います。一方で、日本の登山は山岳信仰からはじまっていて、修験道などでは、頂上に立つことよりも山で自分が変わっていく過程に重きを置いています。伊藤さんのお話と重なる部分がありますね。ぼく自身も10代の後半から20代の間に、本当に様々なアウトドアのフィールドで多くのことを経験して、体を十全に使って移動していく旅に身を投じていきました。その延長で、今もこうしてフリーランスで写真を撮りながら世界を歩き続けています。日本列島はもちろん、今回展示させてもらっている北極圏などから都市の雑踏に至るまで、地球を縦横に旅してかれこれ30年くらいが経ってしまいました。
伊藤:きっとこれからも旅を続けられると思うのですが、石川さんが旅に出る理由は、ズバリなんでしょう。
石川:ぼくは、世界のことを自分の身体で知りたい、知覚したいっていう気持ちがすごく強いんですよ。今って、何かわからないことがあると、スマホとかで簡単に調べられて、簡潔な文章を読んだだけで知っているつもりになってしまう。でもそうじゃなくて、やっぱり自分の目で見て、自分の耳で聞いて、匂いとかも感じながら、五感を通じて目の前の世界に直に触れていきたいな、と。誰かが書いた情報を読んで知っているつもりになるのではなく、身体を通じて、実感を伴って理解したい。実際に歩いて、見て、聞く。旅をするってことは、そうやって世界に触れていく行為ではないかなあ、と思うんです。伊藤さんの場合はどうでしょうか。

伊藤:結構そのことについては、僕もよく考えるんですけど、この間、北海道の天塩川でカヌー旅をした時に、1個答えが出た感じがしました。僕にとって旅は、「自分の変化」だなって思いました。カヌーを漕いで雨の中を数日かけて河口を目指している間に、顔にかかる雨粒や風や音の感覚など、どんどん自然を感じる解像度が上がっていく。旅ではないですが、例えばクライミングに行ったときも、最初はなんのルートも見えないのか、何度かトライした翌日には、昨日見えなかった岩の突起や足場が勝手に目に入ってきたり。そういう変わったなという瞬間が生まれるのがすごく楽しいですね。自然は、そんな自分が変化するチャンスを与えてくれる場という感覚です。
石川:そこは共感できますね。自分を変えていくのって結構大変じゃないですか。 小さい子どもはいろんな環境に自分なりに適応していくけれども、大人になっていくと凝り固まった軸みたいなのができちゃうから、自分を変えていくことってそんなに簡単なことじゃないんですよね。でもアウトドアのフィールドに出ると、自分の周りの環境は変えられないから、自分を変えていくしかない。街に住んでいたら、寒いときは暖房を入れたり、ストーブをつけたりして周りを暖かくして快適な空間を作る。けれど、ヒマラヤなどの極地では、周りの環境を変えることはできないから、自分自身が空気の薄い高所の環境に順応していかないといけない。寒いときも、体を温める装備をちゃんと身につけなきゃいけないし、何より寒さ自体に慣れていかなきゃいけない。周りを変えるんじゃなくて、なるべく自分を変えていかないと立ちゆかなくなっちゃう。こうした考えは30年くらい旅を続けてきて思い至ったのですが、伊藤さんは3年くらいでその考えに辿り着いているんですね。
伊藤:まだ多分入り口ぐらいだと思うんですが、今のお話を伺っていて、やっぱり自分の体で知りたいという好奇心がピュアなものとして強くあるんだなと感じました。僕も、自分を変えるという意味では、新しいことをして自分を追い込みたいところはあって、そういう気持ちがいろんな原動力になったりもするんですけど、同時に居心地のいいところに居続けたいという気持ちもどこかにあったりして、いつも葛藤があるんです。石川さんは、新しい挑戦をするときにそういった葛藤や怖さみたいなものはありますか?
石川:知らない場所に行きたい、知らないものを見てみたい、自分の目で確かめたいっていう気持ちは、いつも持っています。たしかに、「怖くないんですか?」ってよく聞かれるんですが、「怖い」っていう感情は決してネガティブなものだと思ってなくて。新しいものに出会うことは多少なりとも怖いことでもあるし、でも同時に出会いの喜びとも紙一重だと思っています。そして、これはぼくの願望でもあるのですが、これからも常に自分自身が変化できる状態でありたいっていう気持ちがあります。実際、旅をしていると、そうせざるを得ないっていうか、変わらない自分でいると逆に旅が進まなくなっちゃったりするので。常に変幻自在でありたいですね。

自分の感覚を、そのまま写す
伊藤:なるほど。その変幻自在に変わっていく中で、石川さんにとって写真ってどういうものなのか、お伺いしたいです。ブルーボトルコーヒーのジャーナル『Small Talk vol.4』にて執筆いただいた巻頭コラムの写真は知床だと思いますが、行くきっかけはあったのですか?
石川:『Small Talk』では知床半島の羅臼について書かせて頂きました。知床には年に2~3回は通っています。2001年にエベレストに登った後、次はどこに行こうか、と思って、国内にも目を向けるようになって、初めて知床に滞在したら好きになってしまって。行こうと思ったきっかけは、アラスカと似ていたから。アラスカのデナリ国立公園にも熊が多く出没するんですが、テントに熊を寄せ付けないために、テントから離れたフードロッカーという鉄のコンテナに食料を入れておくんですね。知床はデナリ国立公園と同じように熊の王国で、同様のフードロッカーが羅臼岳などに備え付けられているんです。日本でそんな環境があるのは、知床くらいなんじゃないかな。

伊藤:石川さんがシャッターを切る瞬間って、思考的なものでしょうか、それとも直感的ですか?
石川:思考じゃなくて、完全に体の反応で撮っていますね。構図や光がどうの、ではなく、その瞬間の反応で撮った写真の方がぼくは面白いと思っています。言葉で説明できるものは、言葉を使って説明すればいいので、言葉が追いつかないものを撮りたくて。伊藤さんも最近新しいカメラを使って写真を始められたそうですね。
伊藤:そうなんです。先日友人が持っていたライカを借りたとき、カメラを構えて、実際に撮るまでの一連の動作が、すごく新鮮な体験だったんです。ファインダーを通して向こう側を見るっていう独特の感覚にハマりました。
石川:ぼくが使っているカメラは単焦点のレンズがついていて、ズームなどはできません。だから、遠くにあるものは遠くに写り、近いものは近くに写ります。人物を撮るときも、たとえば相手と初対面で遠慮して近寄れないとしたら、そういう近寄れないという距離感が写る。ズームを使うと、そうした距離が不自然に縮められたりして、ぼくはちょっとズルをしている感覚があるんですよね。遠いものは遠くに写ればいいし、近寄れないんだったら、その近寄れないっていう距離が写ればいいと思っていて。その方が写真として面白いんじゃないかなあ、と思っています。
伊藤:確かに、見たものを良い感じに残そうっていう意識がひとつ入ると、写真がつまらないものになっていく感覚、わかります。
石川:写真って、後から見返すとそのとき気づかなかった何かも偶然に写り込んでいたりする。いろいろな発見が、時を経て二重三重に起こったりするのが面白いんですが、変に意識して作り込んだ写真だとそういう発見がなくなって消費されて終わっちゃうんですよ。

写真家、石川直樹として
伊藤:石川さんのこれまでのお話を伺っていると、新しいものを見つけに行ったり、未知に触れていきたいというピュアな原動力に冒険家を感じたのですが、石川さんがご自身の肩書を写真家とされている理由ってなんでしょうか。
石川:昔から冒険とか探検の話が好きで、本もたくさん読みましたし、実際に冒険家、探検家、登山家、いろんな人に会いに行きました。そういう方達に話を聞くと、本当にすごいんですよね。彼らに誰よりもリスペクトをもっているが故に、冒険家とか探検家って自分で名乗ることを憚られるというか、自分はまだそこまでは到達していないっていう感覚がいつもあります。あとは、カメラを持たずにフィールドに行くモチベーションはそこまではなくて、ちゃんと自分が見たものを記録しておきたいし、写真で残しておきたいって気持ちが強くて。だから「職業はなんですか」と聞かれたときに、消去法で写真家と答えるのが、一番正直な回答だと思っています。冒険や探検を好きすぎるが故に、自分にはまだ名乗れないなという気持ちがありますね。
伊藤:カメラを持たずにどこかにいくことはないですか?
石川:ないですね。人間ってどんどん忘れていくものなので、なるべく自分が見たものを忘れたくないっていう気持ちがあります。後から写真を見返すと、過去の旅が別の方向に広がっていくこともあって。シャッターを切ったときのことを思い出したりしているうちに、新しい旅へと繋がっていくような感じがぼくには面白い。旅と写真は、自分のなかで切っても切り離せなくなっちゃいましたね。

伊藤:写真を通して自分の世界が広がる感覚、とても共感できます。今回「旅とコーヒー」というテーマで『SmallTalk』を刊行しているので、コーヒーに関することもお聞きしたいのですが、石川さんが旅をする中で、どんなときにコーヒーを飲みたくなりますか?
石川:少し立ち止まって、思考を巡らせたいときですかね。エベレスト街道の途中の街に、「シェルパバリスタ」っていう新しいカフェができて、そういうところでぼーっとしてると、移動しているときとまた違う感覚になる。別の空気に触れて気分を変えたいときとか、考えを巡らせたいときにカフェに行きますね。昔は海外の山岳地帯でコーヒーを飲もうとすると、コーヒーというより、ただの黒いお湯みたいなのが出てきたものですが、今では本格的なコーヒーが飲めるようになって嬉しいですよ。
伊藤:高所とか、自然の中にいると感覚も鋭くなるので、コーヒーの味わい方も街で飲むときと変わりますよね。コーヒーを抽出するときの温度など、アウトドア環境で淹れると店舗で作るのとは全然違って変数要素が大きいのですが、それはそれで良さがあります。
石川:伊藤さんは職業的にもたくさんコーヒーを飲まれていると思うのですが、飽きたりはしないですか?
伊藤:コーヒーって本当にいろんな産地があって、その土地のことを知っていくと、たとえば「ここは水が足りない環境だから、こういう処理をしていて、だからこういう味になるんだ」っていう新しい発見の広がりがあって面白くて飽きないですね。そんな風にコーヒーはもともとが自然とつながっているものでもあるので、僕自身はどれくらい荷物が重くても、アウトドアのフィールドにはコーヒーキットを持っていきたいと思っています。
石川:ネパールも、今コーヒー豆を作り始めたりして、新たな産地としても面白いことになっていますね。今度「シェルパバリスタ」のコーヒーを飲みに、ヒマラヤのトレッキング、標高5000メートルぐらいのところまでぜひ一緒に行きましょう。
Photography: 半田淳也 AND WHAT NOT design
Text: 田尻侑里 RCKT/Rocket Company*