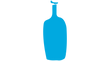Crafting Quality from Seed to Cup
ブルーボトルコーヒーが大切にしている理念の一つに、”Seed to Cup(シードトゥカップ)”という言葉があります。この言葉は、一杯のコーヒーが世界中の農園でのコーヒーチェリーの栽培にはじまり、収穫、精製処理、生豆の選定、輸送、そして焙煎、抽出というプロセスを経て、カップへ注がれてゲストの元に届くまでの長い道のりを表しています。ブルーボトルコーヒーでは、グリーンビーンバイヤー(生豆のバイヤー)が季節ごとに最もおいしいとされる旬のコーヒーを厳選、自社焙煎所でロースターが豆の個性を最大限に引き出した焙煎を行い、そしてカフェで熟練のバリスタが”一杯のおいしいコーヒー”をゲストへお届けする、”Seed to Cup”を丁寧に積み重ねていくことで世界をつなぐことを目指しています。
今回のブログでは、”Seed to Cup”の長い道のりの中でも、普段カフェからは見ることのできない焙煎プロセスにおける”一杯のおいしいコーヒー”の品質のこだわりについてご紹介します。ブルーボトルコーヒーがグローバルで構える4つの自社焙煎所のひとつ、北砂ファクトリー(東京都江東区)でシニアロースタリー リーダーを務めるKentaさんにお話を聞きました。


北砂ファクトリー シニアロースタリー リーダー Kentaさん
KITASUNA FACTORY
北砂ファクトリーは、日本全国、そして香港、シンガポールのブルーボトルコーヒー 計36店舗(2025年11月時点)で提供されるコーヒー豆の焙煎拠点です。ここには季節ごとに世界各地の農園から届くコーヒ豆が集まり、およそ20通りのレシピで焙煎してそれぞれの個性を丁寧に引き出しています。ファクトリーには2台の熱風式焙煎機があり、一度に35キロのコーヒー豆を焙煎することができます。カフェからのオーダーに合わせ、毎日およそ40回、1トンを超えるコーヒー豆が焙煎されています。焙煎を終えたコーヒー豆は丁寧にパッキングされ、各地のブルーボトルコーヒー カフェへと届けられます。そして今日も、バリスタの手によって”一杯のおいしいコーヒー”としてゲストの皆さまのカップへ注がれています。



“Seed to Cup” of Roasting
ブルーボトルコーヒーでは、”Seed to Cup”における全てのプロセスを丁寧に管理し、品質へのこだわりとサステナビリティへのコミットメントを原動力としています。中でも焙煎プロセスの品質づくりは、日々積み重ねていくフィードバックによって磨かれていきます。「私たちロースターチームは、届いたコーヒー豆の個性を引き出すために、日々の焙煎を通してトライアンドエラーを重ねています。その積み重ねが”一杯のおいしいコーヒー”をつくるためのクオリティにつながります。」とKentaさんは話します。
ロースターチームの朝は、前日に焙煎したコーヒー豆のカッピングという作業から始まります。カッピングは、コーヒー豆の品質やテイストを評価する、全世界で標準的なテイスティング方法です。焙煎したコーヒー豆を少量ずつカップに取り分け、挽いた豆にお湯を注いで香りを確かめ、スプーンで啜ってテイストのポイントを評価します。こうして日々の焙煎クオリティを確認し、次の焙煎につなげるフィードバックを積み重ねていきます。
Coffee Cupping at Blue Bottle Coffee
ゲストに一杯のコーヒーが届くまでに、ブルーボトルコーヒーでは大きく4回のタイミングでカッピングが行われています。それぞれに目的があり、”Seed to Cup”の一連のプロセスを通して品質の確かさを担保しています。
1回目は、買付け時のタイミング。農園やエクスポーター(輸出企業)からグリーンビーンの買付け時に、コーヒー豆の個性や品質を確認するために行います。
2回目は、農園やエクスポーターからブルーボトルコーヒーへ納品されたタイミング。買付け時の評価と同じ品質で届いているかを再確認します。
3回目は、焙煎後のタイミング。自社焙煎所で焙煎した翌日に、焙煎ごとのクオリティを細かく確認します。これはプロダクションカッピングと呼ばれ、合格点を超えたものだけがカフェ、そしてゲストの一杯として届けられます。
4回目は、カフェ提供前のタイミング。バリスタがゲストへ提供するコーヒー豆の個性の理解を深めるために行うものです。
グリーンビーンバイヤーやバリスタが行う、コーヒー豆の個性を見出すカッピングがいわゆる”加点方式”だとすると、ファクトリーでのプロダクションカッピングは”減点方式”でのチェックだと言えます。プロダクションカッピングは、ターゲットの範囲内で焙煎されたコーヒー豆について、焙煎時間や温度、焙煎度といった測定データをロースターの味覚や嗅覚などの感覚と照らし合わせ、豆の持つ個性が一杯のコーヒーとして最大限に表現できているかを見極める、非常に繊細な作業です。




プロダクションカッピングの様子。前日焙煎したコーヒー豆ごと(1バッチ)に、少量ずつ同量のサンプルを取り分けて焙煎のクオリティを確認していきます。フレグランスやアロマ、フレーバー、酸味、ボディ、甘み、アフターテイストのポイントを、温かい状態と時間をおいて冷めた状態の両方で評価し、5点満点からの減点方式で判断します。
プロダクションカッピングは、焙煎クオリティによるコーヒー豆の微細な変化を正確にとらえるため、評価するロースター自身が”変化しない状態”で臨むことがとても重要です。ブルーボトルコーヒーでは、毎日決まった時間に同じ場所で、変動要素を極力排除した環境のもと、前日に焙煎したコーヒー豆のカッピングを行います。味覚や嗅覚に影響を与えうる体調や感情の揺らぎを整えるため、健康管理はもちろん、カッピング前の朝食は毎日同じものを摂る、刺激物の摂取は避ける、さらにはカッピング前のスタッフとの会話にさえ気を配ると言います。また、複数名でカッピングを行う場合は、評価中は黙々と作業を進め、終了後に初めて意見交換を行います。他者のコメントに引きずられることなく、常にニュートラルな判断を保つためです。

「朝の静かな空間でコーヒー豆の香りを確かめ、お湯を注いだときのコーヒー粉と混ざり合う音に耳をすませ、香りとともに湯気が立ち上る様子を眺める。この瞬間はなんて贅沢だろうと日々感じます。」とKentaさんは静かに語ります。
Roasting is trial and error
こうして日々のカッピングを通じて焙煎クオリティを丁寧に確認し、その後の焙煎へのトライアンドエラーを繰り返していきます。
現在、ホリデーシーズン限定でご提供しているウィンターシングルオリジンコーヒー「エチオピア・ハンベラ・メタド・ナチュラル」を例にお話します。焙煎データはターゲットの範囲内でしたが、カッピング後に「さらに果実感のある個性を引き出せるのではないか?」という意見がロースターチームの間で交わされ、焙煎レシピの調整を行いました。焙煎翌日のカッピングでは、従来の焙煎レシピのもの、調整を試みた焙煎レシピのものを比較し、狙い通り果実感のある酸味が引き出されているか、またその他のテイストポイントとなる甘みや質感とのバランスは保たれているかを丁寧に検証しました。焙煎データの数値上では問題なくターゲットをクリアしているため、どちらのコーヒー豆もカフェへ自信を持って届けられるクオリティです。それでも毎日のカッピングを通してトライアンドエラーを積み重ね、コーヒー豆そのものが持つ個性をより引き出す焙煎を追求していく。その歩みこそが、”一杯のおいしいコーヒー”を追求した”Seed to Cup” を支える大切なプロセスなのです。
焙煎は、科学で未解明の領域を多く含む”正解のない作業”です。焙煎を行う土地の温度や湿度といった気候条件、焙煎機の種類や性能、ロースター自身の個性、さらには生豆のその年の個性やコンディションによる水分値など、多くの繊細な要因によって仕上がりは変わります。だからこそ、一般論や数値だけにとらわれず、経験から得られる感覚を頼りに日々目の前のコーヒー豆と真摯に向き合う。そうしたトライアンドエラーの積み重ねこそが、”おいしい一杯のコーヒー”へとつながっています。
 ウィンターシングルオリジンコーヒー「エチオピア・ハンベラ・メタド・ナチュラル」のサンプルバッチ
ウィンターシングルオリジンコーヒー「エチオピア・ハンベラ・メタド・ナチュラル」のサンプルバッチ 北砂ファクトリー ロースターチームの皆さん
北砂ファクトリー ロースターチームの皆さん
“Seed to Cup"as a Continuous Cycle
好きなコーヒーの生産地を尋ねると、これまでは長らくケニア産のコーヒーと答えてきたと言うKentaさん。しかし、さまざまな産地のコーヒー豆を焙煎してカッピングを重ねるうちに、それぞれの持つ個性をより鮮明に感じられるようになり、自身の好みも自然と広がってきたように感じると話します。「変わらずケニア産のコーヒーは好きですし、特別な思い入れもあります。ただ、他の生産地の素晴らしいコーヒーとの出会いを重ねるうちに、自分の中の境界が少しずつ低くなっていきました。特に、ここ10年のアジアのコーヒー生産の成長には目を見張るものがあります。そして何より、特定の生産地に限らず、それぞれの季節に迎える“旬のおいしさ”に心惹かれるようになりました。コーヒーは農作物です。それぞれの生産地で栽培されたコーヒーチェリーが旬の季節に収穫され、確かなクオリティコントロールのもと海を越えて日本に届いていることに、とてもワクワクします。」と語ります。
一杯のカップへ注がれてゲストへ届けられる頃には姿を変えているコーヒーですが、本来の姿はコーヒーチェリーという果実です。農作物であるコーヒーチェリーには、それぞれの生産地での旬の季節があり、さらには同じ農園、同じ品種であっても、年ごとに変化する豆の持つ個性があります。その変化する個性を”一杯のおいしいコーヒー”として最大限に表現するのが焙煎のプロセスです。
「焙煎プロセスでは、生豆そのもののクオリティを上げることはできません。だからこそ、栽培や精製処理の段階で高いクオリティを持つパートナーからグリーンビーンバイヤーが生豆を買付け、ロースターがその豆の持つ個性を最大限に引き出した焙煎を行い、バリスタが”一杯のおいしいコーヒー”としてゲストへ届ける。良いフィードバックを積み重ねることで、翌年にも同等以上のロットを買い付けることができ、生産地のクオリティ向上にもつながっていきます。」
”Seed to Cup”は一方向ではなく、サステナブルに循環するサイクルなのです。
ブルーボトルコーヒーの日本上陸当初より、共に歩みを進めてきたKentaさん。今年で日本上陸10周年を迎えたブルーボトルコーヒーについて、過去10年とこれからの10年をこう語ります。「10年続けてきた焙煎の経験値があるからこそ、新たな焙煎にトライアンドエラーをすることができる。この積み重ねができることは、コーヒーブランドとしても、ロースターとしても、とても幸せなことです。とはいえ、各産地でのコーヒーチェリーの収穫は年に一度。10年という年月も、コーヒーの収穫の回数で言えばわずか10回に過ぎません。だからこそ、この先の10年も、その先の10年も、私たちはより良い焙煎のために、トライアンドエラーを続け、当たり前ではない”一杯のおいしいコーヒー”への追求を続けていきます。」

Kentaさん / 北砂ファクトリー シニアロースタリー リーダー
2015年ブルーボトルコーヒー日本上陸当初の清澄白河ロースタリー&カフェから、現在の自社焙煎所・北砂ファクトリーに至るまで約10年間、“一杯のおいしいコーヒー”を支える焙煎に携わる。現在はシニアロースタリーリーダーとして3名のロースターを率いるロースターチームのヘッドロースターとして、日々の焙煎からカッピング、ブレンド開発まで幅広い領域を担当している。趣味はスパイス活動。
Special Cupping Class
この度、2025年12月13日(土)、14日(日)に清澄白河フラッグシップカフェで開催する「ホリデーマーケット」にて、ロースターによる「カッピングクラス」を特別開催します。* 焙煎の現場で行われるカッピングついて、ロースターが直接ゲストの皆さまへレクチャーし、一緒にカッピングをご体験いただける貴重な機会です。豆の個性を引き出すロースターの視点をカッピングを通じてご体験いただけます。
さらに本クラスは、同じ清澄白河の地にカフェを構えるスペシャルティコーヒーロースター Allpress Espresso Japan (オールプレス・エスプレッソ・ジャパン)と共同開催し、両ロースターがそれぞれの焙煎のこだわりについてお話しするとともに、両カフェのシーズナル限定のブレンドをカッピングしていただけます。複数のコーヒーを比較しながら、じっくりと味わっていただくことで、コーヒーの奥深さや楽しみ方の広がりを感じていただけるようなクラスです。
コーヒーは好きだけれども詳しくはないという方、カッピングを初めて体験してみたい方、そしてもっと深くコーヒーについて知りたい方まで、どなたでもお楽しみいただける時間となっています。皆さまのご参加をお待ちしております。
*ご好評につき、「カッピングクラス」は満席となりました。
「ホリデーマーケット」では、本クラス「カッピングクラス」のほかにもマーケット限定のワークショップや、大切な方への贈り物、ご自身へのご褒美となるような特別なアイテムをご用意して皆さまをお待ちしております。詳細はInstagram公式アカウント(@bluebottlejapan)の投稿よりご確認ください。
今回のブログでは、ブルーボトルコーヒーのクラフトマンシップが息づく自社焙煎所・北砂ファクトリーで、焙煎クオリティを支えるカッピングの作業についてご紹介しました。普段カフェからは見ることのできないファクトリーでのこだわりが、“Seed to Cup” の道のりの中で “一杯のおいしいコーヒー” へとつながっていることを、少しでも感じていただけていたら嬉しく思います。
ぜひ全国のブルーボトルコーヒー カフェで、世界中の農園から旬の季節に届けられ、そして北砂ファクトリーで丁寧に焙煎された “一杯のおいしいコーヒー” をお楽しみください。